
生成AIと子育て
今日は「生成AIと子育て」について。
もうすっかり私たちの生活に当たり前な存在になってきた生成AI。
活用されている方も多いのではないでしょうか?
生活の中で当たり前に存在しはじめている生成AI
6月は横須賀市内の公立中学校3校にキャリア授業でお邪魔してきました。
そこで生徒さんたちに「何かしらAIを使っている人?」と聞いたらクラスの半分以上の生徒さんが手を上げてくれました。時代ですね。
私たちが良く使っているLINEもついにLINEAIというサービスが提供されるようになりましたよね。
1日の使用回数に制限はあるものLINEユーザーなら誰でも気軽にAIを無料で使用できます。
大人よりももしかしたら子どもたちの方が生成AIを使用することに抵抗がないかもしれません。
実際うちの息子もPCを開いて画面半分でchatGPTを開き、プログラミングコードを生成し、もう半分でPythonを開いてそのコードを入力して何やら自分であれこれ作って遊んでいます。エラーになったらまたGPTに修正させて…の繰り返しです。
私にはまったくチンプンカンプンの世界ですが、産まれた時からデジタルに囲まれている若い子たちはもうこの世界がデフォルテなのかもしれません。
AIの進化は本当に素晴らしく、まったくコードが書けない私のような素人でもGPTやFigma、Layermateを駆使したら3,4時間くらいあればあっという間に簡単なWEBプロダクトが完成したりします。
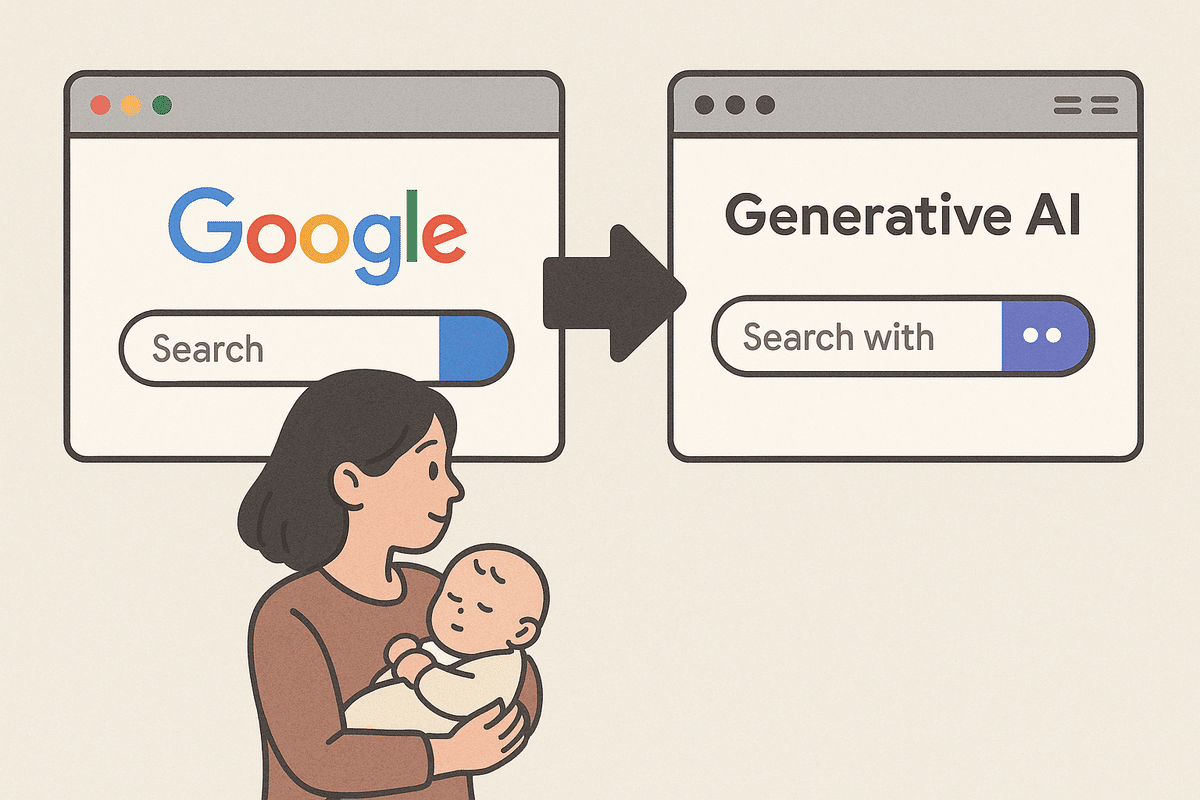
これまであれだけGoogleの検索を使用していたのに、私もGPTをインストールしてからはほとんどGoogle検索を使用しなくなりました。
翻訳機能に関しても同じで、Google翻訳よりもGPTに細かく指示した方がナチュラルな表現で翻訳してくれます。
生成AIによって確実にタスク処理の時間は軽減され、自分の時間を他のことに使えるようになりました。本当に秘書が一人となりにいる感覚です。私はGPTが作ったものを丸っとそのまま使用することはもちろんありません。(note投稿はすべて自分で書いてます。)生成されたものからさらにブラッシュアップしていく感じですが、作業効率の良さは抜群。
子育てにおいての生成AIの役割
そこで改めてふと思ったこと。
これから先の子育てにおいて生成AIがどんな役割をしていくのだろうか?
まず第一にもうLINEでも無料で使えるAIが標準装備される時代。
子育てで何か人に聞きたい。相談したい。情報を知りたい。
こういった時にこれからのママたちはもしかしたら最初に相談するのは人や検索、SNSではなく、AIなのかもしれません。
ビックデータの中から一番その人の質問に適したものを探し出してくれます。しかもAIは使用すればするほどユーザーの好みを理解し、育ちます。
行政関係の諸手続きなども恐らくどんどんDX化されていき、スマホ一つで完了するサービスが増えていくはず。
保育園や幼稚園、こども園、ベビーシッターや一時預かりなど条件を入力したらAIがおススメを紹介してくれて、あとは見学に行くだけ。そんな日も近くなるかもしれません。
そうなると私が提供している「親子のためのサードプレイス」いわゆる「居場所」の役割はどうなっていくのか?
それでもリアルな居場所が必要なはず
AIが進化し、技術が進化しどんどん育児関連商品は便利になっていきます。
先に書いたように簡単な質問はスマホ上でAIが答えてくれて、必要であれば話相手にもなってくれる。
それでも私は子育てにおいて居場所は絶対に必要だと考えます。
どれだけ世の中が便利になったとしてもいつの時代もママから産まれてくる赤ちゃんの状態は一緒です。
6年子育てに関わる事業をしていてひとつわかったことがあります。
それはいつの時代になってもママたちの子育ての悩みの本質は変わらないということ。
授乳がうまくできない。
泣き止まない。
離乳食を食べてくれない。
偏食がひどい。
言葉がなかなか出てこない。
AIに一般的な対処法を提示されることはあっても、それはあくまで一般的な話。
今を生きている赤ちゃんや子どもにAIが直接何かをしてくれることはありません。
生成AIの話をしておきながら、古臭いと言われるかもしれませんが、子どもを育てている時の母親の勘ってすごいんですよね。
こういう様々な育児のあれこれに、子どもを育てながらだんだんと「あ、きっと原因はこれ」とか「今は何も声掛けしないでほおっておいた方がいい」など、親なりの勘が育ってきます。
生身の人間を育てている時に起こる様々なトラブルシューティングはロボットやAIはまだまだ人間には勝てないと感じています。
ぬくもり、あたたかさ、心を寄せる、思いやり、共感、察する…など。
人間だから赤ちゃんや子ども、ママたちに出来ること。
人は互いに思いやることで成長し、理解し合えるものだと思います。
AIに使われるのではなく、AIを使うことでうまれた余白を人にしかできないことに使う。
人と人が実際に会うことで得られるものは機械同士で生まれたものとそもそもの価値は違う。
リアルに会える場の必要性はAIの進化が進むこれから逆に大切になるのかもしれません。
「居場所」を提供する側として、今の世の中の動きにアンテナを張り続け、これからママになる世代の人たちが置かれている環境を理解しながら足を運んでみたくなる居場所作りにこれからも励みたいと思います。